2025.02.28
アジェンダ
- デザインのいう仕事について
- ポートフォリオとは
- 構成のまとめ方について
- 本日のまとめ
- 本日のまとめ
point
デザインとアートは違う
デザインという仕事について
アートとは
- 表現者、あるいは表現物
- 精神、感覚の変動を得ようとする活動
- 文芸、美術、音楽、演劇、映画など芸術を指す
アートとデザインの違い
- アート(芸術)は感情、創造、表現
- デザインは計画、成り立ち、構成すること
デザインとは
- 目的設定、計画策定、仕様表現からなる一連のプロセス=目的
- 美しさ、使いやすさ、の実現のため創意工夫すること
- 図案、模様、設計、造形、構想
- 創造的な行為(サッカーのセットプレーなど)
デザインの目的
美しさ、使いやすさ、課題解決のための創意工夫
デザインのゴール
課題、願望解決、実現に導く思考法
デザインの大切さ
理念、文化を世の中に伝えていく「コミュニケーション手段」
国や街の雰囲気、食事の色、好む色の組み合わせなど独自の文化
デザイナーに向いている人
- オリジナリティのある人
- 美的感覚、時代感覚がある人
- 手先の器用さ、緻密さ、計算能力、我慢強さがある人=細かく地味な作業が多いから
- デザインやアートをクライアントに主張するための説得力を持つ人
デザインはパクリか
定義はない
盗作に明確な基準はない
レイアウトは目的が同じであれば似てしまうもの
デザイナーにとって必要なスキルとは
- 分析力
- デザイン知識
- 発想力
- 情報収集力
- 情報整理力
- 情報分析力
- 課題解決力
→感覚的なものより与えられた情報の中から知識や調査を経て形にする能力がある方がいい
デザインセンスを磨くには
- 自分の感性を見直すこと
- 様々なデザインに触れること
- 相手「ターゲット」を考える
→問題解決につながる - 単純に考えられるように整理する
→複雑であればあるほど伝わりづらくなる - デザイナーの思考法を参考にする
→成功した人の作品をよく見て思考する
アート=自由な発想
デザイン=目的がある
達成するためのもの
設計・計画・企画・構想・目的・意図
デザイナーの仕事
- グラフィック
- WEB
- CG
- ファッション
- UI/UX
- DTP
- ゲーム
- エディトリアル
デザインする力とは
- クリエイティブ
- センス
- デザインスキル
- 企画力
- 構成力
- 創造力
- 伝える力
- 伝達力
アート =なるべく制限のない状態の自己表現
デザイン=問題解決、与えられた制限の中で求められる最大の結果を出すためのプロセス
*仕事を受けたうえでアートをしてしまうと問題解決はできない
アート思考のデメリット
個の内側のアイデア価値を掘り下げていく行為なので他者との共通認識を持つことが難しい
→チームプレイに適さない
デザインの世界ではアート思考は難しい
アート思考とデザイン思考
ユーザー目線に立ち課題解決を行うものがデザイン思考
思考する側の独自性、オリジナリティある発想や答えを導くのがアート思考
*デザイン思考+アート思考でないとおもしろい作品は生まれない
*柔軟に考え思考する
アートとデザインの思考の流れ
シンプルな発想は伝わりやすい
お客様の求めるもの(お客様が気づいていない部分も)提供する
*デザインはユーザー(お客様)の課題・困りごとを解決すること
→問題解決能力を上げる!
問題解決能力を上げるには
デザインを「言語化」する必要がある
頭の中のことを相手が理解しやすいよう整理する
わかりやすい言葉で伝える
複雑な考えをシンプルにすることで言語化しやすい
言語化の3つのメリット
メリットその1
- アイデアの一貫性を保つことが出来る
- 言葉にすることで認知でき、記憶が残る
- 反復する、悩み、考えることで習慣化
- どうして丸にしたか、赤色にしたかなど言語化できるようにする
メリットその2
- 自分の思考を客観視出来る
- 方法として筆記開示がある
- 現段階で書いてまとめ、後からさらに書くと深く自分の思考について認知できる
メリットその3
- 要約力が身につく
- 一言で伝える力が身につく
- 何を伝えたいか可視化できる
- 不必要なものを排除出来る
- 相手に伝えるために整理する力が身につく
デザイン論について…3つの視点
レイアウト(配置)
どこに何をどう置くか言語化できるといい
例)目立たせたいものなので大きく
見出しなのではっきりした色で … など
フォント(文字)
書体選びを言語化する
例)なぜその書体にしたのか
なぜその大きさなのか
*目的達成のために、読みやすさ、伝わりやすさを考える
カラー(配色)
配色はデザインのイメージだけでなく、人の感情に作用する
NFTアート・ブロックチェーンとは
デジタルアートに鑑定書、所有証明書付きブロックチェーン上で発行、取引されるデジタルデータ
→固有のデジタルデーター作成・資産価値を付与することが出来る
NFTアートのすごさ
ブロックチェーン上で保管
→コピー、改ざんが出来ないので資産価値が生まれる
NFTとアートの関係
現代アート作品の価値が向上する可能性がある
NFTアートはお金がかかる?
出品にはお金(ガス代)がかかるが、NFT化だけなら無料
ブロックチェーンは誰が管理?
特定の管理者はいない
偽造は不可能
暗号資産を取り扱う参加者全員が共有
保存、管理=分散型台帳
まとめのめ
デザインを学ぶためには
・様々な作品を目にする
・作品を言語化
レイアウト(配置)
フォント(文字)
カラー(配色)
これらを意識し観察、分析を行っていこう
言語化の例
・和風の作品には和風のフォントを使う
・みんなで集まるイメージを〇で描く
・人の目は左上から右下に移動することを踏まえ、導線を意識してデザインする
・一本の線上でイメージを二分したり??
・本人(お客様)の雰囲気をカラーに反映
など無理やりでもいいので、言語化することで自分の中(自分も知らない自分)の理屈、考え方のくせ、引き出しが発見される
本日の講義の感想
講義を受け、まず最初に考えたのが自分の弱点についてでした。
訓練校に来てデザインを考える際、私自身の引き出しの少なさ、言語化はおろか発想すらも乏しいのではと気づく場面が多々ありました。ある意味致命的な状況だなと思ったのですが、弱点を知り意識することや補完することで、デザインをする際の指標を自分なりに確立することが出来るかもと思えました。
私の弱点
・発想に乏しい
・つまらない作品が出来ている
・カラーが苦手
・直感的に描いてしまっていたので言語化が出来ていない
弱点の対策を考えてみる
・発想に乏しい対策→有名な作品を見つけ、作者の目標設定を探ってみる
・つまらない作品対策→自分の好きをたくさん見つけ言語化してみる
・カラーが苦手→色彩検定の勉強を取り入れ、色の心理などを学ぶ
・言語化できない→制作においてのゴールを定め逆算しながら描いてみる
以上、自分の弱点を探り対策を取りながら、さらにデザインを学びたいと思います。

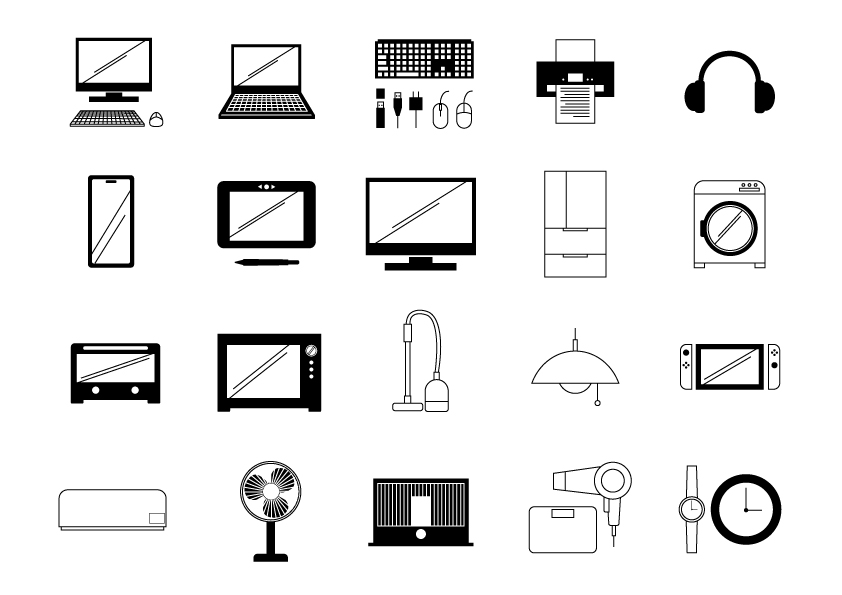
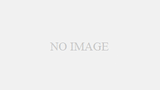
コメント